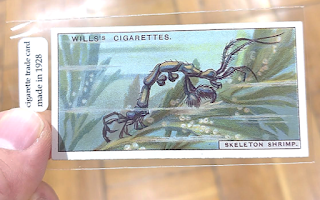またヨコエビが採り上げられた書物が出版されました。
— 仲村康秀・山崎博史・田中隼人(編) 2025.『カラー図解 水の中の小さな美しい生き物たち―小型ベントス・プランクトン百科―』.朝倉書店,東京.384pp. ISBN:978-4-254-17195-2(以下、仲村ほか, 2025)
出版社は異なりますが『小学館の図鑑NEO POCKET プランクトン』の系譜のように思えます。ボリュームが充実し、ベントス要素が強化された感じでしょうか。なお、ページ数は2倍ちょっと、価格は10倍になっています。
仲村ほか (2025) を読む
解説のないものも入れて、掲載端脚類は以下の通りです。この他に、表紙に姿があるリザリアライダーの話題も紹介されています。
- Orientomaera decipiens(フトベニスンナリヨコエビ)
- Ptilohyale barbicornis(フサゲモクズ)
- Monocorophium cf. uenoi(ウエノドロクダムシと比定される種)
- Pontogeneia sp.(アゴナガヨコエビ属の一種)
- Caprella penantis(マルエラワレカラ)
- Simorhynchotus antennarius
- Vibilia robusta(マルヘラウミノミ)
- Oxycephalus clausi(オオトガリズキンウミノミ)
- Melita rylovae フトメリタヨコエビ
- Grandidierella japonica ニホンドロソコエビ
- Podocerus setouchiensis セトウチドロノミ
- Sunamphitoe tea コブシヒゲナガ
- Leucothoe nagatai ツバサヨコエビ
- Jassa morinoi モリノカマキリヨコエビ
- Caprella californica sensu lato トゲワレカラモドキ
- Caprella andreae ウミガメワレカラ
- Caprella monoceros モノワレカラ
- Themisto japonica ニホンウミノミ
- Phronima atlantica アシナガタルマワシ
- Lestrigonus schizogeneios サンメスクラゲノミ
※仲村ほか (2025) に明示の無い和名は()内に示しています。
なかなかボリュームがあります。
だいたいが筆者のKDM先生が撮られた写真のように見受けられます。先生の主な研究テーマである藻場の生態系と端脚類に関するコラムもあり、エンジニア生物や物質循環といった観点から端脚類を見ることもできる構成となっています。KDM研における最新の分類学的知見を反映して「ウエノドロクダムシ」の同定に慎重になっている、といったライブ感があるのもポイント高いです。
白眉はなんといってもヨコエビからクラゲノミまで揃い踏みしているところにありますが、驚愕したのは、堂々と旧3亜目体制に基づいている点。海外の文献では Lowry and Myers (2017) に基づく現在の6亜目体制を追認する動きが一般的となっている印象がありますが、日本人研究者は亜目を省略するなど距離をとる雰囲気がありました。「国内では不人気」という言い方もできるかもしれませんが、それを形にしたのは非常に画期的です。
新知見を採用しないというと時代に取り残されている感じもしますが、6亜目体制は「形態に忠実であることを謳っている一方で例外を意図的に無視しており、自己矛盾している」「かといって系統を反映させる気はない(遺伝的知見との整合性を意図したような例外の扱いではない)」「形態的な明朗性・系統反映のポリシー・過去の慣例の全てを犠牲にしたわりに直感的に分かりにくく、使い勝手が良い場面が特にない」といった問題があります。Lowry and Myers (2017) は大量の分類群について形態マトリクスを作成して議論を試みた労作であることは間違いないのですが、このように中途半端な改変を行うより、「尾肢の先端に棘状刺毛があるグループとそうでないグループを発見した」というような発表に留めておいたほうが、論文として評価は高かったのではと思います。端脚類全体を網羅する下目・小目といった新概念を提唱しつつ、結局所属不明科を残したままというのも片手落ちの感があります。そろそろ10年になりますが、特に優れた点の無い体系のため安定して使い続けられる保障がないという判断から、採用に慎重になっている人がいるものと、個人的には理解しています。
こういった分類のややこしさについても、仲村ほか (2025) は論文を引いて示しています。
仲村ほか (2025) の印象を一言で表すとすれば「本棚にベンプラ大会」。タイトルからすると「生物ルッキズムを含んだ写真集」のように思えますが、写真はカットの物量こそあれど思いの外小さく、種や話題のチョイスの渋さ・ガチ感が光ります。前述のような分類学の議論をはじめ、ベントス・プランクトン学会大会で聴かれるお馴染みのテーマや学術的な課題が、当然のように並べられています。細菌の項で培地の写真が並んでいるのにはドン引きしました(誉め言葉)。マニアックな生物に対して、その珍奇さよりここに収録されるべき学術的意義に立脚して選定・解説しているのが、プランクトン学会とベントス学会が全面バックアップしているだけのことはあるなと、思いました。375ページに上る大著でありながら、水圏生物の花形である魚類が4ページしかないというのも特徴的だと思います。
ただ、解説は非常に平易な文章に仕上がっており、文字数もそれほど多くありません。「写真をパラパラ見る」用途として問題はないかと思います。これだけ幅広い生物群を、「小さく美しい」というテーマに沿って網羅的に平等に扱おうと試みた書籍の例はあまりないものと思われます。『深海生物生態図鑑』のようにグラビアの美麗さや物量で押してくるタイプではないのですが、微生物やメイオベントス群集といった、ともすれば味気ない専門書の中の住人であった生物を、ビジュアル図鑑の世界へ招き入れたというのは、大きな出来事のように思えます。中学生から大学まで、生物分類や水棲生物研究全般に興味のある学生には、興味をそそるだけでなく基礎知識の勉強にもなる一冊でしょう。
『小学館の図鑑NEO POCKET プランクトン』のコスパの良さが異常なので、こちらのほうがエッセンスだけ摂取したい方にはお勧めできるかもしれません。ただ、当然のことながら 仲村ほか (2025) において情報量は格段に増えていますし、学名の併記や参考文献もしっかり押さえられており、実用性を付与されているのは間違いありません。
ちなみに、「ウミガメワレカラ」という和名が学名と明確に対応された出版物は初めてだと思います(和名の初出は青木・畑中, 2019)。そういった文脈でも参照され続ける文献と思われます。
最後に、仲村ほか (2025) における端脚類の掲載箇所を詳細にご教示いただいた朝倉書店(公式ツイッターアカウント)様に、この場をお借りして篤く御礼申し上げます。
<参考文献>
— 青木優和 (著)・畑中富美子 (イラスト) 2019.『われから: かいそうの もりにすむ ちいさな いきもの』. 仮説社, 東京.39pp. ISBN-10:4773502967
— 藤原義弘・土田真二・ドゥーグル・J・リンズィー(写真・文)2025.『深海生物生態図鑑』.あかね書房,東京.143 pp. ISBN:978-4-251-09347-9